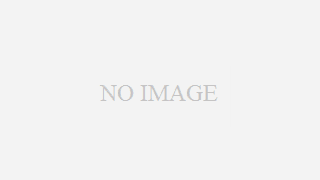 行動経済学
行動経済学 選択肢が多すぎると売れなくなる?選択のパラドックスが示すマーケティングの盲点
現代の市場では「選択肢が多いこと」が一見すると顧客にとっての利点のように思われます。豊富なラインナップを揃えることは、多様なニーズに応えるための当然の戦略と考えられてきました。しかし心理学や行動経済学の研究は、必ずしもそうではないことを示し...
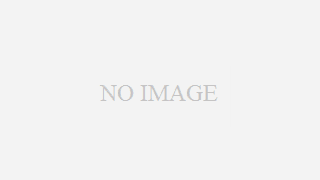 行動経済学
行動経済学 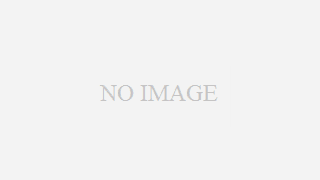 行動経済学
行動経済学 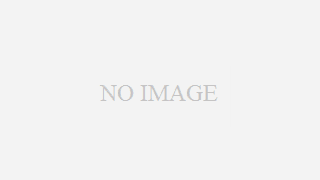 行動経済学
行動経済学 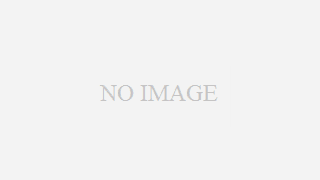 行動経済学
行動経済学 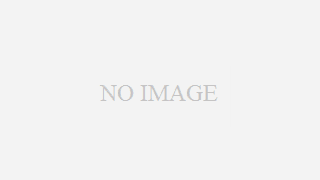 行動経済学
行動経済学 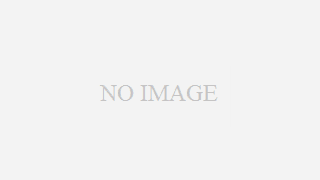 行動経済学
行動経済学 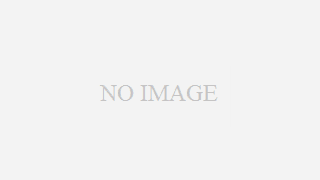 行動経済学
行動経済学 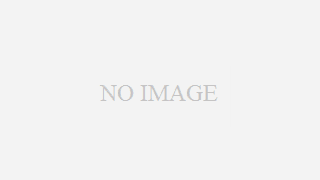 行動経済学
行動経済学 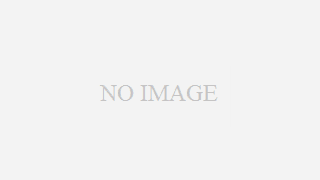 行動経済学
行動経済学 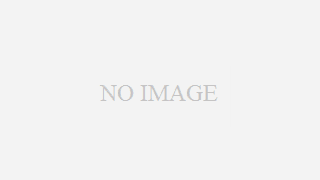 行動経済学
行動経済学